罹災証明書と被災証明書の違い
罹災(り災)証明書・被災証明書はどちらも、「自然災害によって何らかの被害にあいましたよ」ということを公的に証明する書類です。
(![]() 思いっきり大ざっぱな説明です)
思いっきり大ざっぱな説明です)
保険金の支払いや公的な支援を受けたりする時に、この証明書を持って「確かに被災したよ」ということを証明するわけです。
受けられる支援や免除は色々な種類があります。
(お住まいの地方自治体によっても違います)
例えば義捐金の給付だったり、保育所の保育料減免だったり、住民票や免許証の発行手数料を無料にしてくれたり。
受けようと思う支援ごとに、「り災証明書」が必要だったり「被災証明書」が必要だったり、ケースバイケースになります。
では、り災証明と、被災証明はどう違うのでしょうか。
これも大ざっぱな説明になりますが、り災証明書は不動産(主に建物)に関する被害を証明し、被災証明書はそれ以外の被害(例えば家財道具とか)を証明する書類です。
また、り災証明書は被害の状態(全壊・半壊・一部損など)を証明しますが、被災証明書は「被災した事実」を証明するものなので、被害の大小は関係がありません。
もっと言うと、り災証明書はどの自治体でも似たような条件で発行されますが、被災証明書は自治体ごとに発行の条件が違ってきます。
(発行の明確な基準は決まっていません)
なんと、被災証明書が存在しない自治体もあります。
……私が住んでいる仙台市のことです![]()
自治体によってかなりバラツキがあるように思います。
私も、り災証明と被災証明の違い、どうやったら証明がとれるのか、証明書発行までの流れはどうなるのか全く知りませんでした![]()
実際に必要になってからバタバタと証明書を請求してしまい、とても反省したので、各証明書について詳しく説明を残しておきたいと思います。
罹災(り災)証明・罹災(り災届出証明)被災証明とは
分かりにくいと思うので、私なりに図解してみます。
自治体によって細かな違いがあると思うので、詳細はお住まいの市町村のHPなどで確認してくださいね。
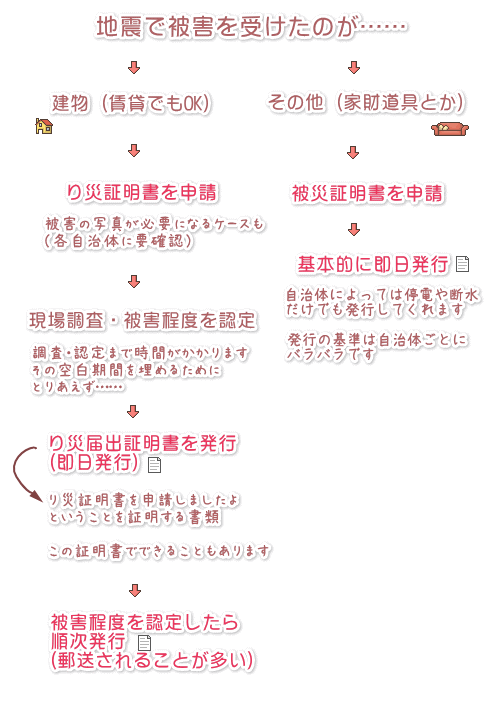
自治体によって多少の差はありますが、おおむねこんな感じです。
3つの証明書について簡単にまとめてみます。
- 建物に関する被害の大きさを証明する書類
(全壊・半壊・一部損など) - どのくらいの被害を受けたか、原則として調査員が現地調査を行います
- 調査後の発行になるので、申請から発行まで間があきます
(我が家は3か月かかりました)
そのため、「り災届出証明書(り災届出の申請をしたことの証明)」が発行されます - 被害の程度に応じて受けられる支援が異なります
- り災証明を申請しましたよ……ということを証明する書類
- 支援の内容によっては、この証明書で受けられるものもあるので確認が必要です
- 「被災した事実そのもの」を証明する書類なので、被害の大きさは関係ありません
- 即日発行されます
- 証明書の発行基準が自治体によってバラバラです
何をもって「被災した」というのかの定義があいまいな感じ?
家財道具が壊れたりすることを条件にする場合もあれば、「断水・停電」だけでもOKな場合、とりあえず災害のあった日に住んでいればOKという自治体もあります。 - 被災証明書自体が存在しない自治体もあります
仙台市の場合は、り災届出証明書が被災証明書の代わりになります。
各証明書の発行手数料は無料です。
自治体によってかなり扱いが違うので、詳細については各自治体のホームページなどをご覧ください。
なお、各証明書は複数枚取っておくことを強くお勧めします!
保険、高速道路の無料化、災害支援を受けるため……などなど、要所要所で証明書の原本が必要になることがあります。
私も最初、1部しか申し込みをしなかったんだけど、窓口の係員さんから
「3枚は取っておいたほうがいいよ」
と強く勧められたので3枚取得しました。
最終的に原本が必要になったのは2枚で、その他はコピーを利用しました。
アドバイスをくれた係員さん、大阪市からヘルプで来てくれた方だったんですよね。
阪神の震災を経験された方だったのかな……本当に感謝しています。
